SilverStone RM21-308 ラックマウントケース 組立レビュー
前回に引き続き、SilverStoneのラックマウントサーバーケース RM21-308を使ってファイルサーバーを組み立ててみました。
前回の記事はこちらです。
今回はこれらを使いました。
| 型番 | 価格 | 購入店舗 | |
|---|---|---|---|
| ケース | SilverStone SST-RM21-308 | \41,394 (2020/2/11時点) | Amazon.co.jp |
| CPU | Intel Pentium Gold G5400 | \6,820 | ツクモネットショップ |
| MB | ASUS ROG STRIX B365-G GAMING | \11,999 | ツクモネットショップ |
| メモリ | DDR4 16GB | \0 | (メイン機から拝借) |
| 電源 | Antec NeoECO GOLD NE650GOLD | \8,110 | ツクモネットショップ |
| SSD(システム用) | Crucial BX500 120GB | \3,180 | ツクモネットショップ |
| HDD(データ用) | WD Red WD40EFRX-RT2 | \15,169 ×8 | ツクモネットショップ |
| SAS HBA | Broadcom LSI SAS 9211-8i | \10,399 (2020/2/13時点) | Amazonマケプレ (PlayGround0138) |
| Mini-SASケーブル | iSAS-7373-HT/.5m | \3,960 ×2 | Oliospec |
| OS | FreeNAS | \0 | |
| 合計 | \211,164 |
構成
今回使用するケースは、2Uラックマウントのケースでありながら、通常のMicroATXマザーボードやATX電源が使えますので、通常のパソコンパーツで組むことにしました。
CPU
Intelの現行世代のものからチョイスしました。作ろうと思っているファイルサーバーは個人で使うもので、特段高負荷になったりはしないと思いますので、このG5400で充分でしょう。
マザーボード
無難にASUSのものから選びました。ネットワークがIntelのチップのものを選んだ結果、ゲーミング用マザボになってしまいました。無駄に光ります。
データ用HDD
Western DigitalのNAS向けHDD、WD Redシリーズの4TBのものを8台用意しました。4TBは、Redの中では容量単価が高いので微妙だったのですが、ほしい容量と予算を考えてこれにしました。
SAS HBAボード
HDDはケースのフロント面から搭載しますが、内部側はMini-SASケーブルで接続しますので、SASのHBAやRAIDカードが必要になります。今回は、FreeNAS用としては定番のLSI SAS 9211-8iを選びました。組み立て中に、先日の記事で紹介したファームウェア変更を行っています。ファームウェア変更は別記事にまとめていますので、合わせてご覧ください。
Mini-SASケーブル
SAS HBAとケースのHDDバックプレーンとの間は、Mini-SASケーブルで接続します。今回の場合は、両端がSFF-8087のHost to Targetケーブルを使用します。オリオスペックさんでは各種SASケーブルを取り扱っていて、似たケーブル(Host to Host)もあります。オリオスペックさんによると、通常はHost to Targetケーブル(末尾がHTのもの)を使用するらしいです。
電源
このケースでは、長さ160mmまでのATX電源が使えます。今回は、長さ140mmのATX電源で、Antec製の650W GOLD電源を使いました。後述しますが、ワットチェッカーで消費電力を測ってみたらピークが140Wくらいでしたので、もっと小さいので良かったかもしれません。
その他
その他はコストダウンのため、メモリはメイン機から借りてきて、システム用SSDは安価なものを選びました。メモリはそのうち増強しようかなと。
また、OSは無料で使えるNAS用OSである、FreeNASを使用しました。
組み立て
組み立てを動画にまとめてみました。今回はケースの紹介が主ですので、マザーボードの仮組みとOSインストールは省いています。見出しや記事中の時間リンクをクリックすると、その部分からYoutubeで再生します。
マザーボードを取り付ける(動画00:16)
このケースは、MicroATXかMini-ITXマザーボードが使えます。利用するマザーボードに合わせてナットをつけて、マザーボードを取り付けます。
利用するナットとネジは、ケースに付属する「For MB」のものを使用します。マザーボードのサイズによって必要なナットの箇所が異なりますので、マザーボードの説明書を確認しながらナットを取り付けていきます。
ナットを取り付けたらマザボをセットして、ネジ締めしていきます。
電源の取り付け(動画02:25)
電源を取り付けます。電源取り付け部は、こんな感じになっています。

このケースは、ATX電源の他に2U冗長電源なども使えるようです。ATX電源の場合はそのまま取り付けられますが、冗長電源などの場合は、同梱のブラケットを使用するようです(下図左)。また、今回はケース同梱のネジ(下図中央)ではなく、電源に同梱されていたネジ(下図右)を使用しました。
電源を取り付けるとこんな感じになります。

マザーボードの24ピン、8ピン端子に接続します。

続いて、HDDバックプレーンの電源端子(4ピン ペリフェラル×4カ所)を接続します。この電源には、4ピン端子が3つしかありませんので、市販の分岐ケーブルを使って4カ所に接続しました。
フロントパネルの線を接続(動画05:20)
続いて、フロントパネルの電源スイッチや各種LEDの配線をします。
このケースには、電源スイッチ、リセットスイッチ、電源LED、HDDアクセスLED、ネットワークLED(2個)、USB 2、USB 3の配線があります。説明書にはありませんでしたが、NIC LED(ネットワークアクセスLED)のプラスマイナスは、右上図のようです。これらの線を、マザーボードの説明書に従って接続していきます。
使用したマザーボードにはNIC LED用をピンはありませんので、今回は使用していません。このLEDは通常のLEDですので、他のアクセスランプとして使用することもできます。例えば、下図のようにHBAボードにはHDDのアクセスランプ端子があるので、そこに接続するとHDDアクセスランプになります。
ただし、このケースとこのボードの場合だと、ケースのカバーが閉まらなくなります。また、ケースの前面には、各HDDのアクセスランプが用意されていますので、使用する必要もないでしょう。ということで私は、このLEDは使用していません。

HBAボードの取り付け(動画08:49)
次に、HBAボードを取り付けます。このケースは、ロープロファイルの拡張ボードスロットが4つあります。スロットカバーを外して、ボードを取り付けます。
最初つけたとき、ブラケットの先端がうまくささっていなかったようで、ネジを締めても浮いていました(左図)。本当は右図のように、ブラケットとケースが密着します。
このHBAボードは、ヒートシンクだけついているファンレスのボードですが、割と発熱するようなので、エアフローを確保するため、スロットカバーは全部外すことにしました。
Mini-SASケーブルの接続(動画09:14)
HBAボードとケースのHDDバックプレーンのMini-SASポートにケーブルを接続します。
バックプレーン側の端子は、ケースファンとの間にあって指が入りづらく、挿せませんでした。なので、ケースファンがついているプレートを一旦外してMini-SASケーブルを接続しました。ケースファンのプレートは、プレートの底面とケース側面からネジ止めされています。
ここが一番大変だったので、この接続を一番最初にやった方が良かったかもしれません。

続いて、HBAボード側も接続します。

SSDの取り付け(動画11:35)
このケースは、フロントに8つの2.5インチ/3.5インチオープンベイが8つありますが、それとは別に2.5インチのシャドウベイが2つあります。
今回はそのシャドウベイにシステムドライブ用のSSDを取り付けました。
ケースには2.5インチのトレイがついていますので、一旦外してSSDを取り付けます。使用するネジは、ケース同梱の2.5インチHDD用のネジです。
このケースでは、L字のSATAケーブルは使えませんので、ストレートのSATAケーブルを用意する必要があります。今回は、SATAと電源のケーブルの分岐コネクタを使ってSSDに接続しました。
接続したら、2.5インチトレイをケースに取り付けます。
中身完成(動画13:44)
これで、ケース内部の組み立ては完了です。良ければ、ケースのカバーを閉めます。
ここでは省略しますが、この後起動確認とFreeNASのインストールを行っています。



HDDの取り付け(動画14:19)
フロントの3.5インチオープンベイにHDDを取り付けます。
オープンベイには、無駄なエアフローを防ぐカバーがついています。2.5インチの場合はカバーをつけたままでも大丈夫ですが、3.5インチのHDDをつけるときは、防風カバー(矢印の部品)を外します。外すと右図のようになります。
HDDをトレイに取り付けていきます。2.5インチと3.5インチで使用するネジが異なります。今回は3.5インチHDDをつけますので、ケースに付属する3.5インチ用のネジを使用します。ちなみに、2.5インチの場合は底面から、3.5インチの場合は側面からネジ締めします。
トレイにHDDを取り付けたら、トレイをケースに装着します。
これで、すべて組み上がりました。FreeNASの方でパーティションや共有の設定を行えば、完了です。
起動テスト(動画16:12)
起動・終了の時間を測りつつ、ワットチェッカーで消費電力を見てみました。
起動直後、140Wほどになりますが、アイドル状態では60Wのようです。また、起動は1.5分ほど、終了は15秒ほどでした。
ついでに、やっぱりサーバーケースなので結構ファンがうるさいです。

まとめ
SilverStone RM21-308は、2Uラックマウントでありながら、MicroATXマザーボードとATX電源が搭載可能で、ごく普通のパソコンパーツで8ベイのファイルサーバーがつくれます。
HDDバックプレーンのMini-SASケーブル端子だけは組みづらかったですが、それ以外はどこもアクセスしやすく、通常のフルタワーケースよりも組みやすかったと思います。それでいて、HDDが8つ載せられるようなフルタワーケースと比べると高密度でコンパクトにまとめられます。
注意点としては、前述の「Mini-SASケーブルが挿しづらい(動画09:14)」のと、「L字SATAケーブルが使えない(動画12:52)」、「自宅で使うにはファンがうるさい(動画08:34)」、「あまり流通してない」、「ファンのケーブルがファンに当たってた」あたりでしょうか。
今回かかった費用はトータルで21.1万円、うちHDDが12.1万円です。8ベイのNASキットとして見ると9万円ですので、市販のNASキットより安くファイルサーバーを構築することができます(電源やマザボを見直すとさらに安くなるでしょう)。
全体として、私のニーズにぴったりマッチする良い製品で、とても大満足です。
2020/8/9追記:電源の長さについて
YouTubeで電源の長さについてコメントをもらったので、1枚写真を撮ってみました。今回使っている電源は、AntecのNeoECO GOLD NE650GOLDで、長さは140mmです。

電源の長さは、SilverStoneによると「160mmまで対応」と表記していますので、160mmでも問題なく使えると思います。(もう少し長くても問題ないと思います)
ただ、短い電源の方がコネクタ接続時に手が入りやすいし、余った配線を置いておきやすいです。あまりに長い電源はやめた方が良いかもしれません。




































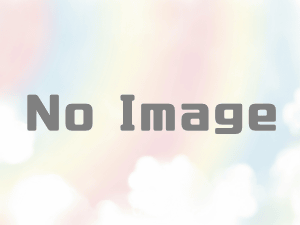









ディスカッション
コメント一覧
YouTubeでコメントした人です、もっと交流を深めたいんですが、メールアドレスを教えてもらってもいいですか?
コメントありがとうございます!
大変申し訳ないのですが、メールアドレスは非公開とさせていただいています。
コメントについては、引き続きこのコメント欄やYouTubeにいただけると幸いです。